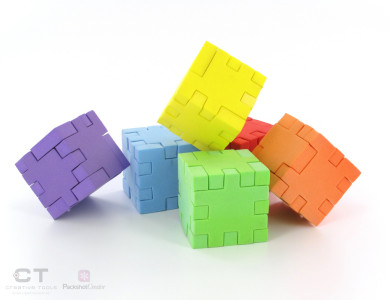
IFRSでは、決算日に差異がある場合の子会社及び関連会社の追加的な財務情報について、差異が3ヶ月を超えない場合に、「実務上不可能な場合」を除いて、作成が要求されています。日本経済団体連合会のIFRS実対応検討会が10日に公表した「IFRS 任意適用に関する実務対応参考事例」では、任意適用会社10社がIFRS適用あるいはその検討にあたって、子会社の決算日が異なる場合に、どのような検討を行い、対応したのかが公表されていたので、今回はご紹介します。
今後、IFRSを任意適用する会社は増加すると予想されますが、決算日の統一と仮決算による対応はグループの親会社の方針しだいであることがよくわかります。
3つの実務対応パターン
決算日の統一と仮決算に対する各社の実務対応は細かい点で異なるものの、おおむね次の3つのパターンに分類できます。
- 子会社の決算日が連結決算日と異なる場合、まず決算日の統一の可能性を検討し、次に仮決算対応の可能性を検討する
- 子会社の決算日が連結決算日と異なる場合、仮決算対応の可能性を検討する(決算日の統一はしない)
- 経営管理上の必要性からグループで決算日は統一済み/進行中(IFRS適用検討の論点としていない)
なお、経団連の資料では仮決算への対応として上記1、2の「2つパターンが見られた」として、次のように分析をしています。
1 つ目は、経営管理上の目的から、IFRS 適用を機に、或いは従来の方針として、可能な限り決算報告期間を統一するパターンである。この場合、可能な限り、子会社の決算報告期間を親会社の決算報告期間と統一し、決算報告期間が統一できない場合には、可能な限り(重要性がほとんど無い、又は、実務的に仮決算を行うことが困難である場合を除き)、仮決算での対応を行っている。このような場合、決算報告期間が相違し、仮決算も行わない子会社は、基本的に、重要性の無い子会社か、実務的に仮決算で対応することができない子会社のみとなる。当該パターンは、日本基準でもIFRS でも、何ら支障は生じない。
2 つ目は、日本基準上、決算期の統一を行っていない子会社について、IFRSの適用において、仮決算での対応を検討する場合である。このケースの場合は、決算報告期間が異なる子会社のうち、影響の大きい子会社(重要性の大きい子会社)についてのみ、仮決算での対応が実務上可能かどうかを検討し、実務上可能な場合に限り、仮決算で対応するパターンである。仮決算での対応が実務上不可能な場合には、基本的に、重要な取引又は事象について、調整が行われている。
(IFRS 任意適用に関する実務対応参考事例P60-61より抜粋・引用)
パターン1:子会社の決算日が連結決算日と異なる場合、まず決算日の統一の可能性を検討し、次に仮決算対応の可能性を検討した会社
グループ企業を一定の条件でフィルタにかけ、決算日の統一を目指すパターンです。仮決算対応となる会社が出ることをある程度想定して判断基準を作成している傾向がある点で共通しています。親会社の経理ガバナンスの強さなども影響しますので、杓子定規に判断せず柔軟に対応しようと考える姿勢が読み取れます。
決算日を統一する目的
| A社 | ・リアルタイムに連結単位の経営情報を把握することにより、グローバル経済環境への迅速な対応を可能にする。 ・四半期開示において、投資家等に対して、タイムリーな情報提供を可能にする。 |
| D社 | ・一体の事業管理単位の実現 ・財務会計、管理会計両面の品質担保 |
| E社 | - |
| F社 | 経営上の重要事項と位置付け 取組み例 ・業務フローの見直し(データ集計の自動化、サブ連結から一括連結処理へ、監査日数の短縮) ・管理会計と財務会計の統合、自動集計機能の向上 |
| I社 | ・連結パッケージ目的 ・IFRS目的 |
決算日を統一する会社
| A社 | 次の会社以外 ・売上高や利益など複数の要素を考慮して子会社の規模が小さく重要性が乏しい子会社 ・追加的な財務諸表を作成することが実務上困難な子会社 |
| D社 | 海外子会社を統括する子会社 |
| E社 | ・決算期統一の経営ニーズがある会社 ・経営ニーズがなくても、定性的・定量的重要性がある会社 |
| F社 | ・子会社(重要性のない子会社を除く) ・関連会社(支配する親会社が他にも存在する場合など実務上不可能な場合に該当することも想定) |
| I社 | ・従来仮決算をしている会社 ・従来技術上の制約から仮決算をしていない会社については、重要性について監査人と再協議 |
決算日を統一する会社のうち変更できない会社の例、理由
| A社 | 現地の法制度やパートナーとの関係等によって変更できない会社 |
| D社 | ・D 社とX 社は決算報告期間が異なっているが、現状の体制で会社法上の法定スケジュールを満たすことは短期的には不可能と判断した。 üまた、D 社グループの事業は比較的季節変動も少なく、マーケットも国内外で切り放されており、報告期間の不一致による影響は限定的であるため、利害関係者の判断を大きく誤らせることはないと判断した。 |
| E社 | 変更が不可能な会社 |
| F社 | 小規模子会社について、決算早期化に伴う品質の確保と要員等のバランスについて実情を把握 |
| I社 | - |
パターン2:子会社の決算日が連結決算日と異なる場合、仮決算対応の可能性を検討した会社(決算日の統一はしない)
決算日の統一の経営ニーズが強くなく、どちらと言えばIFRS対応として仮決算すべきか(できる)子会社の特定にその検討の中心があるパターンです。
仮決算する会社
| B社 | 影響額の大きい会社 |
| C社 | 原則すべての子会社 |
判断基準
| B社 | ・影響額の大きい会社として、連結財務諸表に対する影響額(売上高、純資産、利益剰余金、当期純利益)を評価した。 ・また、内部統制における重要性の取扱いを考慮した。 ・その上で、仮決算の実務上の実行可能性を検討した。 |
| C社 | (子会社の重要性にかかわらず)仮決算が可能であること |
仮決算対応が困難であるとした会社の例
| B社 | ・K 社及びN 社は投資会社だが、いずれも、出資先の最大株主ではないため、出資先に仮決算を行わせることは実務上不可能であることから、K社及びN 社の仮決算は実務上実行不可能であると判断した。 ・親会社と異なる決算報告日である関連会社についても、同様の調査・検討(影響度調査・仮決算の実務上の実行可能性の検討)を行った。結果として、影響額に重要性がある関連会社が1 社あったが、それらの企業も含めて、B 社と異なる決算報告日である全ての関連会社について、会社の特徴や他の主要株主の関係などから、実務上、仮決算等の対応を行うことは困難である。 ・よって、親会社と異なる決算報告日である関連会社について、仮決算を含めた決算期の統一は行わない。 ・但し、修正すべき重要な取引(外貨建貸付借入、配当金、資本連結等)のみ、調整を行った。 |
| C社 | ・実務的に仮決算の調整を行うことが著しく困難な子会社等(これらは全て、重要性の無い子会社である)については、仮決算を行わず、12 月期・1月期決算により連結している。 ・これらの子会社については、重要な取引のみ調整という方針だが、実際は、ほとんど調整を行っていない。 |
パターン3:経営管理上の必要性からグループで決算日は統一済み/進行中(IFRS適用検討の論点としていない)
グループの方針として決算日は統一することを明確に出しているパターンです。
決算報告期間統一方針
| G社 | 日本基準の下で既に決算報股間を変更し、グループで統一を行っている |
| H社 | 経営管理上の必要性から決算報告期間の統一に取り組んでいる |
| J社 | ・子会社は、原則として、決算報告期間を統一する(現地法定決算期間の変更は強制せずに、仮決算を行う方式を含む) ・持分法適用関連会社には、決算報告期間の統一を依頼(期ズレによる重要な差異が発生した場合は、仮決算を行う方式で対応する方針) |
背景
| G社 | ・四半期での業績概要の開示について、期ズレのままでは季節要因等ピントの外れた説明になり、業績をうまく説明できない問題意識があった。 ・従来、内部管理上の数値は期間を統一して行っており、二重で数値を作成する手間の排除に加え、数値を内外で統一することによる透明性の向上を図りたかった。 |
| H社 | ー |
| J社 | ・経営陣からのニーズ(3ヶ月遅れでは、情報が遅く、手を打つのが遅れる/対外説明時に、聞き手の感覚とズレが生じる) ・グローバル統一オペレーションによる業務効率向上(現場レベルでの債権債務の突合、残高調整表の作成や経理部門での連結修正仕訳の作成等、決算報告期間が統一されていれば不要な事務を解消できる) ・IFRS適用に向けた対応 |
決算日統一の裏にあるもう一つの課題(決算早期化)
今回の論点について、個社のアクションとしては決算報告期間を統一するか、決算報告期間を統一しないで仮決算で対応するかに分かれます。どちらにしても従来決算が遅い子会社にとってはインパクトがある話です。
一般的には、仮決算を毎期実施するぐらいなら、決算報告期間を統一した方が中長期の負荷は軽減されるし、ましてや経営管理ニーズを考えれば決算報告期間を統一するメリットは大きいでしょう。
ところで、この決算報告期間を統一する裏では決算早期化という課題があります。今回の実務対応事例の中にもそれを見ることができます。
D社
D 社とX 社は決算報告期間が異なっているが、現状の体制で会社法上の法定スケジュールを満たすことは短期的には不可能と判断した。
(IFRS 任意適用に関する実務対応参考事例P67より抜粋・引用)
F社
【統一に向けた取り組み】
(IFRS 任意適用に関する実務対応参考事例P73より抜粋・引用)
・・・中略・・・
(3) 業務フローの見直し(監査体制を含む)
・・・中略・・・
・監査日数の短縮の検討を監査法人に依頼
G社
【実務上の課題】
(IFRS 任意適用に関する実務対応参考事例P74より抜粋・引用)
規模の大きいサブ連結を実施している会社のレポート提出期限を早める事が最大の課題であり、各社個別の制約よりも、連結決算目的のデータ収集を優先することで対応した。
このように、IFRS任意適用会社における決算日統一と仮決算の実務対応パターンをご紹介しましたが、その裏には決算早期化へ取り組むことが前提となっていることがわかります。






